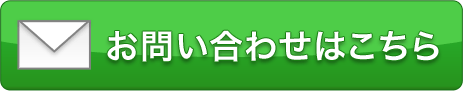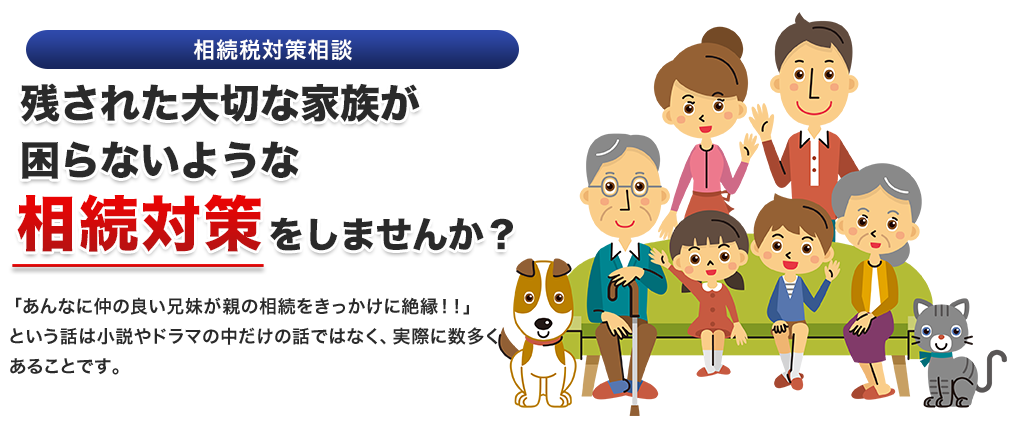
倉持公一郎公認会計士事務所

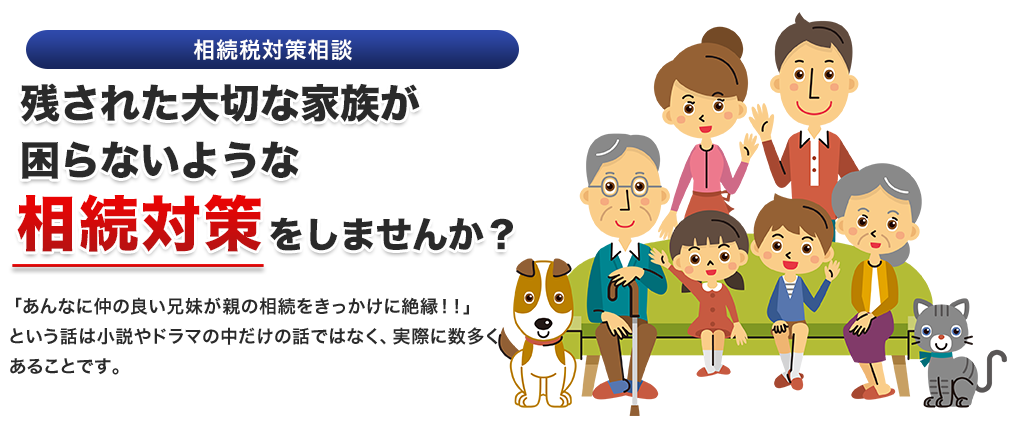
倉持会計事務所が考える相続対策

上記のように相続対策には遺言書作成や納税対策 等がありますが、まずは相続対象となる財産を把握する必要があります。
まずは、ご自分の財産(預貯金・不動産・株式 等)どのくらいの資産があるのか調べてリストを作ります。
(不動産評価は難しいので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。)
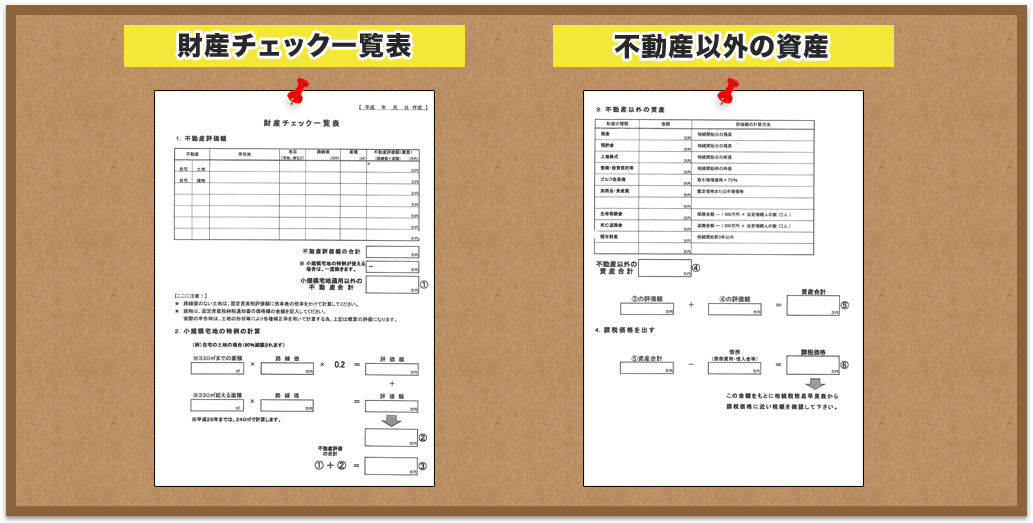
例えば、配偶者がすでに死亡しており、子供が3人いたとします。その3人に均等に分けたいと思うのでしょうか?
それとも、より身近にいてくれた子供に多く相続させたいと思うのでしょうか?
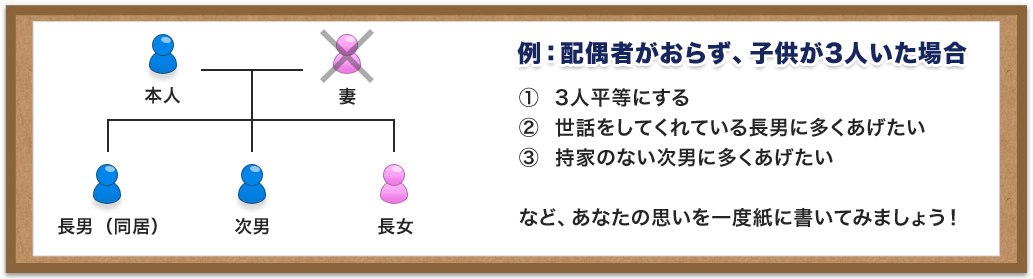
【注意】「遺留分」「寄与分」「特別受益」を考慮して作成しましょう!
どうしてこのような分け方にしたいのか、ご自分の意思をはっきりと伝えましょう!
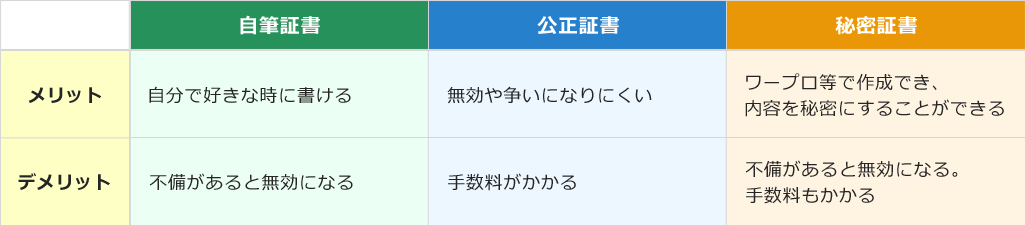
遺言書は、定期的に見直しすることが必要です。
書いたことで安心せずに、1年に1回は財産内容(預貯金・不動産・株式 等の評価価値)や配分の仕方を見直しましょう。
いくつも遺言書がある場合は、一番日付の新しい内容が優先されます。作成しても変更できるので、まず作成してみましょう!
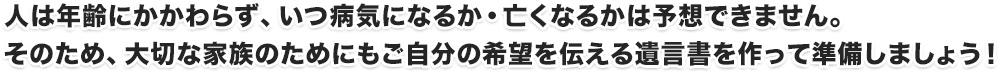
- 1 暦年課税贈与
年間110万円の基礎控除があり、相続が発生する前から贈与し続けることで財産の前渡しができる
- 2 相続時精算課税
2,500万円まで贈与税がかからない(2,500万円以上は一律20%の贈与税がかかる)。
この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税贈与を受けることはできない- 3 住宅取得等資金
父母、祖父母 等から住宅用家屋の購入・新築・増改築のために贈与された資金のうち、最高1,500万円まで非課税となる(平成27年度現在)
- 4 教育資金の一括贈与
父母や祖父母 等が、子供・孫・ひ孫への授業料などの教育費を一括贈与した時、1,500万円を限度に非課税となる
- 5 贈与税の配偶者控除
婚姻20年以上で居住用不動産または居住用不動産の購入資金などの条件に合致すると、評価額2,000万円(基礎控除110万円を合算すると合計2,110万円)を限度に非課税となる
相続税は一括で現金納付が大原則です。
もし、申告期限までに納められなかった場合には、延滞税がかかってきます。
非常に高い年率で余分に税金を払うことになるので要注意!
その為、不動産が多く現金が少ない方は、早めの対策が必要です。
非課税枠のある生命保険を活用する等で、納税資金を準備しておきましょう!
財産に占める割合の大きいのが不動産・・・特に土地です。
同じ土地でも事前の対策をすることにより相続税評価額が変わります。
土地活用には大きく分けて2パターンあります。
1.自宅(小規模宅地の特例)
居住用や事業用に使用している自宅は最高で80%評価減することができます。
この特例を利用するには条件がありますので、早めに税理士等にご相談されることをお勧めします。

2.アパート・マンション経営(貸家建付地)
アパートやマンションを建てると貸家建付地評価となり、土地の評価が減額されます。
養子縁組により法定相続人が増加するので1人につき600万円基礎控除が増加→相続税減額となります。
また、生命保険金や退職手当金の非課税額も増加します。
養子を法定相続人にするには条件があります。
実子がいる場合・・・1人まで
実子がいない場合・・・2人まで
こんなお悩みも解決します!
- Q.遺言書がない時は、どのように遺産を分けるのですか?
- A.遺言がない場合、原則は法定相続分で分割します。但し、相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成すれば、法定相続と違う分割でもOKです。
- Q.どのような資産に相続税がかかるのですか?
- A.預貯金・不動産・株式等が主な相続財産です。住宅ローン等の借金は、相続財産から引くことができます。
- Q.相続税は現金で一括で支払うのですか?
- A.相続税は相続開始から10ケ月以内に現金で一括納付が基本です。その為にも納税資金対策も含めて相続対策しましょう!
- 相続対策プランから申告までを倉持会計事務所に依頼するメリット
- ・必要な情報は試算時に渡し話しているので、とても楽である
- ・対策案も作っているので申告がスムーズにでき、安心して任せることができる
- ・家族間での争いが起きにくくなる
- ・被相続人のことをよく理解している
ご相談からご契約までの流れ
相続に関して少しでも不安になったら、ご相談ください。相談は無料です。
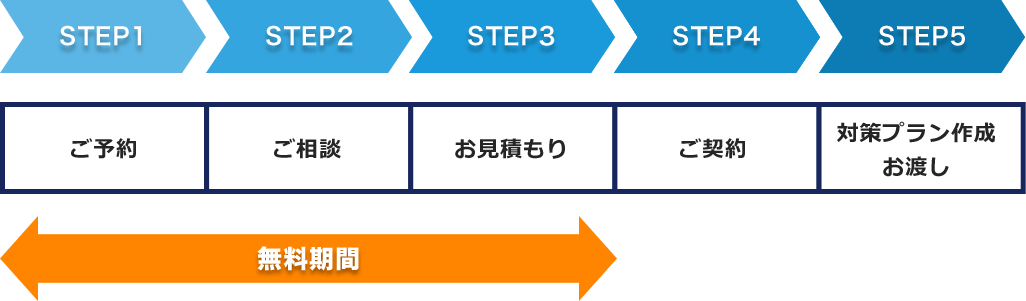
- ①財産評価試算コース 財産評価・相続税簡易試算 5万円(税抜)
- ②財産評価および相続対策プランコース 財産評価・相続税簡易試算・財産評価・相続税簡易試算 10万円~(税抜)
- ※1.
- 対策プラン作成後、万が一相続が発生し相続税申告を当事務所に依頼された場合は、対策プラン手数料を相続税申告書料金より値引きさせていただきます。
- ※2.
- 資料等は基本的にお客様でご準備ください。当方で取り寄せる場合は別途料金となります。